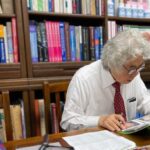【執筆・監修】 阿部 博幸
東京キャンサークリニック理事長
医学博士
一般社団法人国際個別化医療学会理事長
4月から新年度が始まり、環境が変わる方も多いことと思います。新生活への期待と不安で4月は疲れやすくなる時期でもあります。
しかしその疲れやすさの原因は、果たして環境変化からくるストレスだけと言えるでしょうか。
疲れは若い人なら一日で、年齢を重ねた人でも数日も休めば回復するものです。それがいつまでも疲れが残ったり、何をしてもすぐ疲れてしまったりというのであれば、知らず知らずに疲れやすい体を作ってしまう生活習慣があるのかも知れません。それらが相まって、特にこの新しい季節の始まりに疲れやすさを感じるのかも知れません。
疲れやすい体を作ってしまう要因がいろいろとありますので、その対策とともに見てみましょう。
疲れやすい体を作る要因
呼吸が浅い
デスクワークやスマートフォンの使用が増えると、猫背になりやすく、それに伴い呼吸が浅くなります。浅い呼吸では十分な酸素が細胞に行き渡らず、疲れやすくなります。
☑️対策 : 腹式呼吸を意識し、1日数回深呼吸をする習慣をつける。
鉄分の不足
細胞へ酸素供給やミトコンドリアのエネルギー産生に必要な鉄が不足すると、疲れやすくなります。鉄不足は女性だけでなく男性にも見られ、慢性的な疲労感の原因になります。
☑️対策 : レバー、ほうれん草、ナッツ類、魚介類、ひじきなどを意識的に摂る。鉄瓶や鉄鍋を利用する。
糖質過多
白米、パン、麺類、お菓子などの糖質を多く摂ると、血糖値が急上昇します。それを下げるためにインスリンが大量に分泌されると、今度は急激に血糖値が下がり低血糖状態になります。低血糖になると、だるさ・眠気・集中力低下を引き起こし、疲れを感じやすくなります。
☑️対策 : 糖質を摂るときは、血糖値の急上昇を防ぐ食物繊維やたんぱく質と一緒に摂る。
ビタミンB群の不足
糖質をエネルギーに変換するにはビタミンB1が特に重要な役割を果たしています。精製された炭水化物(白米・白パン・うどん等)はビタミンB1が少ないため、このような食品ばかりを摂るとエネルギー産生がスムーズにいかず疲れやすくなります。糖質過多にビタミンB1をはじめとするビタミンB群不足が加わると、エネルギー不足になり慢性的な疲労感が生じます。
☑️対策 : ビタミンB1を比較的多く含む炭水化物は玄米、全粒穀物、豆類、いも類。豚肉、ナッツ類、うなぎなどもビタミンB1が豊富な食材なので意識的に摂る。
ケトンダイエットや糖質制限
体重を減らしたい、痩せたいなどの目的でケトン食や糖質制限食を行う人がいますが、治療目的以外で健康な人がこのようなダイエットを長期間行うと、エネルギー不足になり疲れやすくなるリスクがあります。
☑️対策 : 糖は体にとって主要なエネルギー源であり、特に脳・赤血球・筋肉の正常な機能に欠かせません。長期間の糖不足はミトコンドリアの効率的なエネルギー生産を妨げる可能性があるため、適度な糖質摂取を心がけることが重要。
体温調節機能の乱れ
春先は気温差が激しく、自律神経が乱れやすくなります。これが体温調節を難しくし、無駄にエネルギーを消耗してしまいます。
☑️対策 : 自律神経を整えるために、規則正しい生活リズム、適度に体を動かす、リラックスできる時間を作る、湯船につかることを心掛ける。
睡眠の質の低下
寝る直前のスマートフォンの使用はブルーライトの影響で、睡眠ホルモンと言われるメラトニンの分泌が減少します。入眠に時間がかかる・熟睡できなくなるなど睡眠の質に影響します。また、寝る前のアルコール摂取も、摂取量や体質にもよりますが、入眠は良くなるかもしれませんが、深い眠りが得られにくく、利尿作用で夜中に目を覚ます、いびきをかくなど睡眠の質に影響します。
☑️対策 : できれば寝る2時間前はスマートフォンは見ない、アルコールを飲まないようにするのが理想的。
姿勢の悪さと筋肉のバランスの崩れ
デスクワークの多い人は、前かがみの姿勢や、長時間の同じ姿勢が特定の筋肉を酷使し、疲れを引き起こします。姿勢の悪さによる「巻き肩」や「ストレートネック」は、肩こりや頭痛の原因になります。
☑️対策 : 1時間に1回は肩甲骨を動かすストレッチを行う。デスクワーク時の姿勢を見直す。
水分不足
気温が上がり始める春は、意外と水分補給を忘れがちです。
細胞はさまざまな物質を分泌して細胞間でコミュニケーションをとっているのですが、それが適切に輸送され、対象の細胞に届き、細胞内で応答が引き起こされるには、水分が不可欠な役割を果たしています。水分が不足すると細胞間のコミュニケーションが低下し、免疫応答や代謝、神経活動などに影響が出る可能性があり、これが不調や疲労感の原因につながります。
☑️対策 : こまめに水分を摂取する。ミネラルを多く含む塩も一緒にとること。
ビタミンDの不足
ビタミンDは骨の健康に必要な栄養素として知られていますが、体のエネルギーを作るミトコンドリアの働きのサポート、筋力維持と強化、免疫細胞の活性化、そして抗炎症作用にも関与しているため、不足すると疲れが抜けない、風邪をひきやすいといった症状がでます。
☑️対策 : 日光浴をする、魚、きのこ類、卵、チーズなどビタミンDが豊富な食品を摂る。
疲れの原因になるものを10項目ほどあげてみました。
こういった様々な要因が複合的に絡み合って、疲れやすい体になっていると考えられます。
自分の状態を確認するチェックリスト
さて、もしも疲れやすいなと感じていらっしゃる方がおられましたら、現在のご自分の状態を下記のリストでチェックしていただき、疲れやすい体の原因は何なのかをご自身で特定してみて欲しいと思います。
1. 生活習慣の問題
☐ 睡眠時間が6時間未満の日が多い
☐ 寝ても疲れが取れにくく、睡眠の質が悪いと感じる
☐ 食事の時間が不規則、または栄養バランスが偏っている
☐ 水分をあまり摂らない(1日1L未満)
☐ 運動不足で、日常的に体を動かす習慣がない
2. ストレスや精神的な負担
☐ 仕事や家庭のストレスを強く感じる
☐ 気分の浮き沈みが激しい
☐ リラックスする時間が取れていない
☐ 趣味や楽しみを感じる時間が減った/ない
3. 身体的な不調・病気の可能性
☐ 慢性的な肩こりや腰痛がある
☐ 貧血気味で、立ちくらみやめまいがすることがある
☐ 風邪をひきやすくなど、体調を崩しやすい
☐ 食欲がない、または消化不良を感じることがある
☐ アレルギーや持病がある(例えば、花粉症、糖尿病、甲状腺の問題など)
4. 環境の影響
☐ デスクワークが多く、長時間同じ姿勢でいる
☐ 仕事や家庭での責任が増えている
☐ 冷暖房の影響で、体温調整がうまくいかない
☐ スマホやパソコンの画面を見る時間が長い
☐ 日中はほとんど外にでない
5. 栄養不足・食生活の乱れ
☐ 朝食を抜くことが多い
☐ ファストフードやインスタント食品をよく食べる
☐ ビタミン(特にB群、D、鉄分)が不足している気がする
☐ カフェインやアルコールをよく摂取する
☐ 甘いものを1日何度も食べずにはいられない
最後に
不調で医者を頼るのは悪いことではありませんが、自分にとっての一番の医者は自分自身であることを忘れずにいて欲しいと思います。
なぜなら自分の体は自分が食べたもので出来ており、自分の生活習慣や考えによって体が作られていきます。つまり、自分の体のことは自分が一番よくわかっているはずです。
そして体には免疫という素晴らしい生体防御システムが備わっています。これに頼らない手はありません。意識を細胞レベルに向けて、日夜働き続けてくれる免疫細胞や細菌たちに感謝しながら、彼らが働きやすい体内環境作りを心がけることが大切だと思います。
このコラムを書いている今は、桜が咲き始めています。暖かくなると心身がゆるみ、前向きな気持ちで新しいことに挑戦したくなります。
是非4月から生活習慣を見直し、疲れにくい体作りを始めましょう。
東京 九段下 免疫細胞療法によるがん治療
免疫療法の東京キャンサークリニック
tokyocancerclinic.jp
〒102-0072 東京都千代田区飯田橋1丁目3-2 曙杉館ビル9階
TEL:0120-660-075